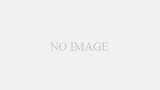生成AIとは?
最近「ChatGPT」や「画像生成AI」という言葉を耳にする機会が増えてきました。これらは「生成AI」と呼ばれる新しい技術の一つです。生成AIとは、コンピューターが学習した情報をもとに、新しい文章や画像、音楽などを作り出す人工知能のことを指します。
生成AIは「猫についての文章を書く」「猫のイラストを描く」といったように、新しいコンテンツを生み出すことができ、「創造的な作業」をコンピューターが担うことができます。
生成AIでできること
- 文章を要約する。構成をする。
- 下書きを作成する
- 音楽や動画のアイデアを作る
このように、学びや日常の中で役立つ場面が増えています。
学生が知っておきたい生成AIの仕組み
生成AIは魔法のように見えますが、実際には大量のデータを学習した結果として動いています。
生成AIの学習の仕組み
生成AIは「理解」しているのではなく、大量のデータからパターンを学び、次に来る可能性の高い言葉や画像を予測している仕組みです。以下、その仕組みを順を追って解説します。
仕組み1 大量学習
- 生成AIは、インターネット上の膨大な文章や画像を使って学習します。この段階でAIは「言葉や画像がどのように使われているか」のパターンを統計的に覚えます。
- たとえば、「リンゴ」という単語は「赤」「果物」「食べ物」と一緒に登場することが多い、ということを学習します。こうして膨大な例から規則性を覚えることで、AIは自然な文章や画像を生成できるようになります。
仕組み2 パターンを学ぶ
- 生成AIは学習の際、犬の画像を大量に見せると「耳の形」「目の位置」「毛の模様」といった特徴を捉えられるようになります。この学習の結果、AIは新しい画像や文章を作るときに、過去のパターンをもとに「らしい形」を生成できるのです。
仕組み3 微調整
- 微調整では、AIがより自然でわかりやすい文章を書いたり、安全で適切な出力を返せるように学習します。たとえば、質問に答える際に「丁寧で読みやすく説明する」ことや、「不適切な内容を避ける」こともここで学習します。
このように生成AIは、百科事典のように知識を正確に持っているわけではなく、「過去の膨大なデータから推測して文章を作っている」のです。
これが「正しいように見えるけれど間違っている答え(AIの幻覚)」が出る理由でもあります。
生成AIの活用例
学習
- 分からないことを調べて、要点をまとめる
- 難しい文章を分かりやすく書き直す
- プレゼン資料のたたき台を作る
武蔵野大学の授業等で生成AIを使用する場合は、大学、及び担当教員のルールに従ってください。また、最終的な内容は出典元、公式WEBサイトで確認し、必要に応じて修正することが重要です。
創作活動への応用(イラスト・音楽など)
- イラストやロゴのデザイン案を作る
- 作詞やメロディのアイデアを得る
- 動画のナレーション文を作る
創作の幅を広げるツールとしても役立ちます。
日常生活での使い方
- 外国語の勉強に活用(英語で会話練習など)
- 旅行計画のアイデア出し
- 趣味やサークル活動での資料作り
日常生活を豊かにするためのサポート役としても期待できます。
生成AIを使うときの注意点
便利な一方で、気をつけたい点もあります。
大学の授業で生成AIを使う場合
大学の授業の参考に生成を使う場合、必ず大学及び担当教員のルールを確認して使用してください。
万が一、ルールに従わない場合は、不正行為と見なされる場合があります。
情報の正確さに気をつける
生成AIは「もっともらしい答え」を返すのが得意ですが、それが必ずしも正しいとは限りません。特に必ず信頼できる情報源と照らし合わせる必要があります。
倫理やルールを守る大切さ
生成AIで作った文章や画像を「自分のオリジナル」として提出するのは不適切です。大学によっては不正行為とみなされることもあります。また、著作権や個人情報の扱いにも注意が必要です。
学びを深めるための使い方
便利な生成AIですが、「答えを出す道具」と考えるのではなく、「学ぶためのサポート役」として使うことが望ましいでしょう。AIが示した答えをきっかけに、自分で調べたり考えたりすることで、学びの質を高めることができます。
まとめ:生成AIとどう付き合うか
生成AIは、日常生活をサポートしてくれる便利なツールです。アイデア出しや、創作活動や日常生活の悩み事の相談まで、幅広く活用できます。ただし「大学のルールを守ること」「正しい情報かどうかを確認すること」「学びを深めるために使うこと」を忘れてはいけません。
これからの社会では、生成AIを上手に使えるかどうかが大切になっていきます。いまのうちから適切に活用し、未来の学びや仕事に役立てていきましょう。